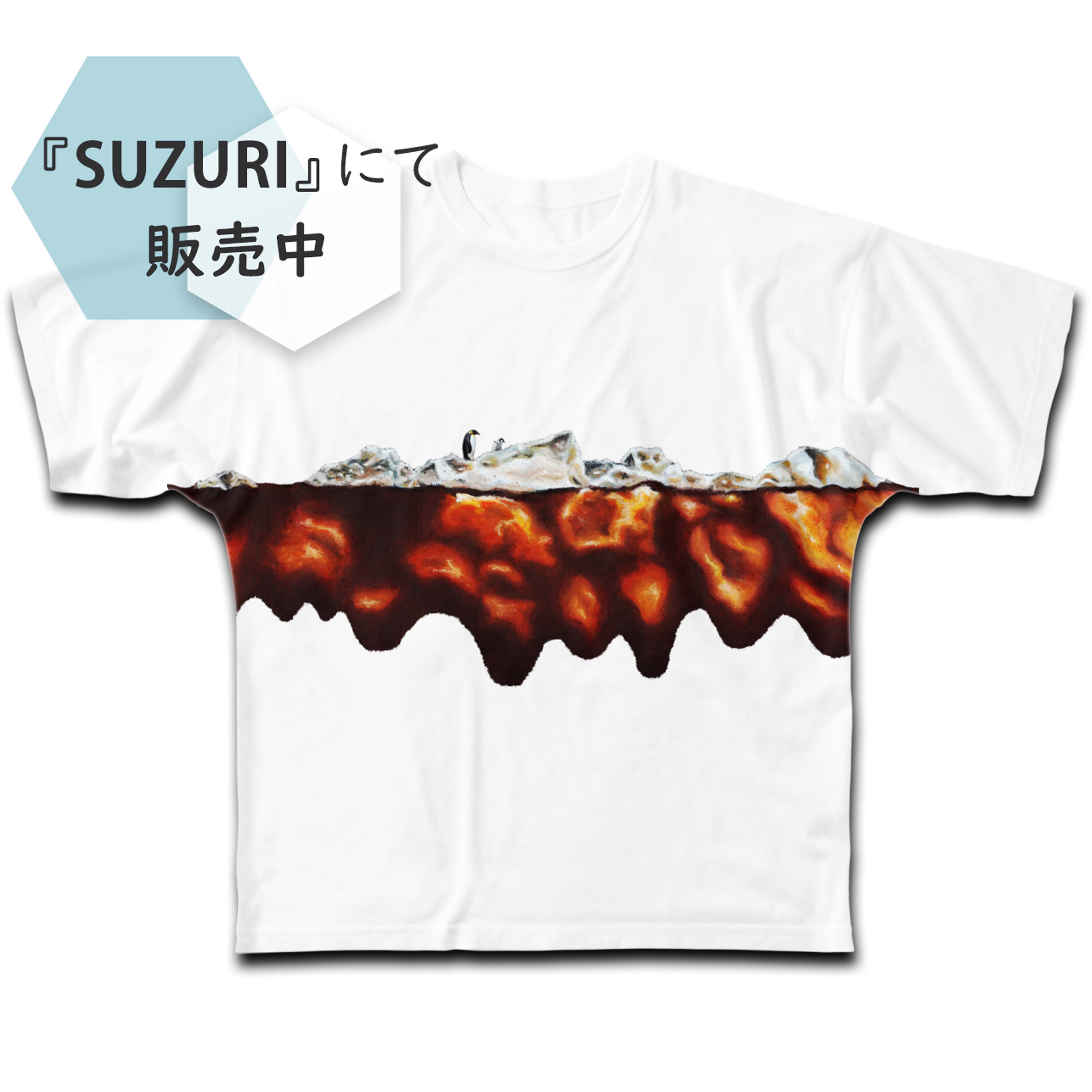Note
2020/09/01 14:52
やってみよう!チョークアート!
【道具編】

【道具編】


なるべくシンプルな基本の工程を、ひとつの作品が出来る工程を追いながら解説したいと思います。
まずは道具からご紹介。
【ブラックボード作り】はこちら
【チョークアートの主な道具】
用意するものは比較的少なく、気軽に始められます。
用意するものは比較的少なく、気軽に始められます。

・オイルパステル
・色鉛筆
・ブラックボード
または・MDFボード
・ブラックジェッソ
・色鉛筆
・ブラックボード
または・MDFボード
・ブラックジェッソ
・水性塗料用ローラー
・コーティングスプレー
・コーティングスプレー
メーカーおよびブランドは様々。
『カランダッシュ』や『ぺんてる』『セヌリエ』『ファーバーカステル』など。
私はぺんてる製品を使用しています。
24色くらいのセットを購入すると、各色味のグラデーションを表現出来ると思います。
『カランダッシュ』や『ぺんてる』『セヌリエ』『ファーバーカステル』など。
私はぺんてる製品を使用しています。
24色くらいのセットを購入すると、各色味のグラデーションを表現出来ると思います。

ネットでも手に入れられます【参考商品】
[ メール便可 ] ぺんてる オイルパステル 25色セット 【 デッサン スケッチ 絵画 油性 コンテ パステル 】 価格:3,300円 |  |
価格:1,584円 |  |
【オイルパステルとは】
顔料に最も近い固形画材・パステル。
『オイルパステル』は顔料をワックスと油で練った物で、クレヨンに似た描き味ですがクレヨンよりも柔らかく伸びが良いです。
油分を含まない『パステル』よりもしっかりとボードに定着するので、塗り込むことでマットな質感も表現が出来ます。
・重ね塗りによる混色が出来るので幅広い色彩の表現が可能。
・発色が良く、耐光性に優れた顔料を使用しているので退色が少ないのも特徴です。
・表面が乾かないので、触れると色が着いたりこすれたりします。その特徴を利用して描くのですが、仕上げにはコーティングが必要です。
また、手に付きやすくそれが口に入る可能性、子供の利用等も考慮して、有害物質を含まず安全性の高い画材という一面もあります。
・色鉛筆<白:下描き用/黒:仕上げ用>
白は下描きに使います。
『オイルパステル』は顔料をワックスと油で練った物で、クレヨンに似た描き味ですがクレヨンよりも柔らかく伸びが良いです。
油分を含まない『パステル』よりもしっかりとボードに定着するので、塗り込むことでマットな質感も表現が出来ます。
・重ね塗りによる混色が出来るので幅広い色彩の表現が可能。
・発色が良く、耐光性に優れた顔料を使用しているので退色が少ないのも特徴です。
・表面が乾かないので、触れると色が着いたりこすれたりします。その特徴を利用して描くのですが、仕上げにはコーティングが必要です。
また、手に付きやすくそれが口に入る可能性、子供の利用等も考慮して、有害物質を含まず安全性の高い画材という一面もあります。
・色鉛筆<白:下描き用/黒:仕上げ用>
白は下描きに使います。
下絵はチャコペーパーで写すことがい多いので、なくても構いません。
黒は仕上げにはみ出した部分を整えたり、ラインや影を入れたりすることで絵の印象を引き締める効果もあります。
鉛筆は線が反射して光るので使わないで下さい。
黒は仕上げにはみ出した部分を整えたり、ラインや影を入れたりすることで絵の印象を引き締める効果もあります。
鉛筆は線が反射して光るので使わないで下さい。


自分は固めのパステルを芯にした『パステル鉛筆』と普通の色鉛筆の2種類を使っています。
パステル鉛筆は一般的な色鉛筆よりも芯が柔らかい分、芯が折れやすく少し扱いづらいのが難点ですが、ボードとの馴染みが良く、線の反射もないので特に黒は愛用しています。
削りやすく尖らせやすい普通の色鉛筆は、似顔絵などの細部の書き込みに利用して使い分けています。
(パステル鉛筆はファーバーカステルの”PITTモノクローム”を使用)
・MDFボード(ホームセンター/100均ショップにあることも)

『MDFボード』とは、木材を繊維状に細かくしたものを圧縮して固めた木板です。
紙と同質でありながら、紙よりはるかに厚くて強く、使いやすいボードです。
表面は滑らかで、中は緻密。家具等にも利用されています。
側面からのクギの保持力や湿気に対してあまり強くありませんが、屋内のディスプレイであればまず問題はありません。
※基本的に扱いやすいMDFボードを使用しますが、表面が滑らかで水性塗料がのる板であれば構いません。
・ジェッソ(画材店)
 『ジェッソ』は、アクリル画の地塗り剤、または絵具そのものとしても使われることがあります。
『ジェッソ』は、アクリル画の地塗り剤、または絵具そのものとしても使われることがあります。下地を覆い、表面を保護し、ジェッソを塗装した板には細かなざらつきが生まれ、絵具やパステルのりが良くなります。
基本的には中粒子のブラックジェッソを塗って黒板を作りますが、豊富なカラーがあり画材屋のアクリル画コーナーに置いてあります。
インクのような匂いが微かにします。
ジェッソに対して20%の水で薄めて使っていますが、時間が経つと分離して粒子が沈殿するので、使う前にまた馴染ませます。
よく使うようなら水と合わせて、ドレッシング用のボトル容器に入れておくと便利ですが、カビが発生することがあるので大量の作り置きはやめましょう。
床やテーブルに付いても拭き取れますが、衣服に付くと取れにくいのでエプロンなどでカバーしてください。
[左:白色ジェッソ(リキテックス)]
[真ん中:ブラックジェッソ(ホルべイン)]今は右の様な袋タイプの販売に切り替えているようです
[右:カラージェッソ”こげ茶色”(ホルべイン)]
【ジェッソ 参考商品】

よく使うようなら水と合わせて、ドレッシング用のボトル容器に入れておくと便利ですが、カビが発生することがあるので大量の作り置きはやめましょう。
床やテーブルに付いても拭き取れますが、衣服に付くと取れにくいのでエプロンなどでカバーしてください。
[左:白色ジェッソ(リキテックス)]
[真ん中:ブラックジェッソ(ホルべイン)]今は右の様な袋タイプの販売に切り替えているようです
[右:カラージェッソ”こげ茶色”(ホルべイン)]
【ジェッソ 参考商品】
ホルベイン カラージェッソ 300mL ブラックジェッソ 【 油彩画 絵画 絵の具 えのぐ 下地剤 地塗り剤 】 価格:990円 |  |
 ・水性塗料用ローラー(画材店/ホームセンター)
・水性塗料用ローラー(画材店/ホームセンター)MDFボードにジェッソを塗る際に使用。刷毛よりもムラなく塗ることが出来ます。
幅があるほうがムラなく塗りやすい。15cmの物を使用しています。
使い始めはスポンジがジェッソを吸うので、ジェッソを多めに用意します。
頻繁に使うなら、洗わずに乾燥防止のためポリ袋にいれておきます。
スポンジにジェッソが馴染んでいる分、少量のジェッソで板を塗りきれるでしょう。
放置して乾燥すると、スポンジに固まってジェッソが定着するので注意。
洗う時は水だけで。洗剤で洗うと次回スポンジから泡がたってしまいます。
・コーティングスプレー
作品の表面をコーティングし画材を定着させる。耐光性・耐水性も持たせます。
『ラッカースプレー』(ホームセンター)
『フィキサチーフ』(画材店・パステルコーナー等)屋内に飾るならこれでもOK
作品の表面をコーティングし画材を定着させる。耐光性・耐水性も持たせます。
『ラッカースプレー』(ホームセンター)
『フィキサチーフ』(画材店・パステルコーナー等)屋内に飾るならこれでもOK
ラッカースプレーは《つや消しクリア》タイプを選んでください。
仕上がりにツヤを出したいのであれば《クリア》タイプもあります。
ホコリなども一緒に定着させてしまうので、表面をきれいにしてからスプレーします。
乾かしているときにも、ほこりなどが付かないよう注意してください。
乾いてから重ねてコーティングすると、より効果的です。
ボードのラッカーの匂いは、しばらくすると消えますのでご安心ください。
ラッカースプレー(カラースプレー)について
ホームセンターの塗料コーナーで手に入りますが、種類がありどれを選ぶか迷うかもしれません。
主に"油性"と"水性"があり、塗料全般において、油性のほうがコーティング力が優るといえます。
しかし、水性といえど乾燥してしまえば雨や水分などによって落ちることはありませんし、油性独特のシンナー臭がないのが嬉しいところ。(ニオイがないわけではありません)
色々試してみて、自分は水性シリコンカラースプレー(クリア・ツヤ消しクリア)が愛用品として定着しつつあります。
※特に油性ラッカーにはシンナーのような強い匂いがあり、吸入すると有害です。製品の注意事項を良く読んでから使用してください。
水性タイプ・フィキサチーフの場合も換気をおすすめします。
【あったら便利】
・クッキングペーパー”エンボスタイプ”
チョークに付いた他の色を拭きとる時に。ティッシュペーパーより破れにくく使いやすいです。
・毛の柔らかい刷毛 ほこりやチョークのくずを払います。
・擦筆(さっぴつ) 紙で出来たペン。ブラックボードに薄い線が引けます。下絵に。
・チャコペーパー(手芸用品店) 紙に描いた下書きをボードに写します。
・スポンジブラシ 写真右から2番目。先にスポンジがついたもの。仕上げ・広い範囲の修正用に。
・綿棒 仕上げ・修正用に。
・マスキングテープ 汚したくない裏面や側面をカバー
その他 ウェットティッシュ・新聞紙など




仕上がりにツヤを出したいのであれば《クリア》タイプもあります。
ホコリなども一緒に定着させてしまうので、表面をきれいにしてからスプレーします。
乾かしているときにも、ほこりなどが付かないよう注意してください。
乾いてから重ねてコーティングすると、より効果的です。
ボードのラッカーの匂いは、しばらくすると消えますのでご安心ください。
ラッカースプレー(カラースプレー)について
ホームセンターの塗料コーナーで手に入りますが、種類がありどれを選ぶか迷うかもしれません。
主に"油性"と"水性"があり、塗料全般において、油性のほうがコーティング力が優るといえます。
しかし、水性といえど乾燥してしまえば雨や水分などによって落ちることはありませんし、油性独特のシンナー臭がないのが嬉しいところ。(ニオイがないわけではありません)
色々試してみて、自分は水性シリコンカラースプレー(クリア・ツヤ消しクリア)が愛用品として定着しつつあります。
※特に油性ラッカーにはシンナーのような強い匂いがあり、吸入すると有害です。製品の注意事項を良く読んでから使用してください。
水性タイプ・フィキサチーフの場合も換気をおすすめします。
【あったら便利】
・クッキングペーパー”エンボスタイプ”
チョークに付いた他の色を拭きとる時に。ティッシュペーパーより破れにくく使いやすいです。
・毛の柔らかい刷毛 ほこりやチョークのくずを払います。
・擦筆(さっぴつ) 紙で出来たペン。ブラックボードに薄い線が引けます。下絵に。
・チャコペーパー(手芸用品店) 紙に描いた下書きをボードに写します。
・スポンジブラシ 写真右から2番目。先にスポンジがついたもの。仕上げ・広い範囲の修正用に。
・綿棒 仕上げ・修正用に。
・マスキングテープ 汚したくない裏面や側面をカバー
その他 ウェットティッシュ・新聞紙など




主な道具を紹介しましたが、やっていく上で自分のやり方や道具が見つかってゆくと思います。
基本だけにとらわれずに、色々と試されるとより世界が広がるのではないでしょうか。